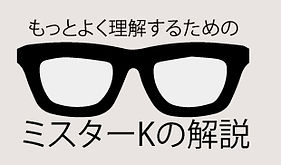連載4-1/本当は楽しくて役に立つことに挑戦したい学生たち。「この指とまれ」は誰がやる?【広島工業大学】
- odlabo
- 2025年6月25日
- 読了時間: 8分
更新日:2025年8月4日
広島工業大学電気システム工学科では、学生の主体的な活動を促すために、学科独自の学生プロジェクト「HIT-ALPs」を立ち上げ、2024年から活動をスタートしています。ここまでは、活動の立ち上げの背景や学科が抱える課題などについて先生方に話を聞いてきましたが、今回のインタビューでは、HIT-ALPs初代団長のYさん(電気システム工学科4年生)と、現団長のSさん(同3年生)に話を聞いてみました。学生主体のプロジェクトに対する思いや、自分たちで考え、行動することへの手応えについて話を聞いてみました。

初代団長・Yさん(左)と現団長・Sさん(右)
――まずはお二人に、それぞれHIT-ALPsに参加する前はどんな大学生活を過ごしていたのか聞かせていただいてもいいでしょうか。Yさんは4年生ということですが、ご自身の学生生活をふりかえってみていかがでしたか?
Yさん 私は3年生の時に大学祭の実行委員長を経験させてもらいました。広島工業大学の大学祭は規模も大きくて、それに伴って予算も責任も大きいものなので、貴重な体験をさせていただいたなと思っています。
――大学祭の実行委員会に入ったきっかけは?
Yさん 高校時代に文化祭委員の活動をして結構楽しい体験になったことや、そういう活動が就職活動などにも役立つかなと思って、1年生の時に入りました。
――どんな経緯で委員長になられたんですか。
Yさん 私が委員長をする年がコロナ明け初の工大祭フル開催だったんです。コロナ前の資料もほぼない状態で、数枚しかない過去のパンフレットを見ながら再現しなければならなくて。やることがわからなければ、早く動かないといけないのに、、責任が重すぎてだれも委員長をやりたがらなかったんです。委員長探しで時間が止まってたんで、自分やるから早く前に進もうっていう気持ちでしたね。
――その次はHIT-ALPsに関わることになったんですよね。
Yさん 松岡先生から12月に突然お話をいただいたんです。学生の自発性を高めることを目的に、電気の面白みを発信できるような活動を始めるので、工大祭実行委員長の経験を生かしていろいろと考えてほしいって言われました。
――HIT-ALPs立ち上げの初ミーティングの時のことは村上先生や松岡先生に聞いています。Yさんたち学生側からいいアイデアを提案されたと伺っていますが、その時のことをお聞かせください。
Yさん 最初は先生たちから「勉強会の企画を考えている」と聞いたのですが、正直、勉強会をやって学生の自発性って出てくるかな?って思って。勉強なんて自分でやると決めた時にやらないと身につかないものだし、大学生が集まっても雑談会になっちゃうし。それだったら、出張授業とか、企業さんと連携した企画とか、そういう体験を通して勉強するほうがいいんじゃないかと思いました。自分たちが教える側になったら、自発的に計画も立てるし、電気の技術について勉強する。そうすれば、自発性も勉強も一石二鳥で身につくと考えて提案しました。
――その提案はご自分の経験に基づくものだったのですか?
Yさん 当時は3年生で、自分の周りは「勉強は自分でやる」というタイプの人ばかりでした。先生たち「自発性」をどのように考えていたのかわかりませんが、勉強では自発性は上がらないのではないかと思ったんです。
――自発性を高めるには効果が乏しいと。
Yさん そうですね。目的がそうであれば、文化祭みたいな雰囲気で自分のやりたいことができたらいいなと思いました。僕が考えている自発性というものは、どんどん自分たちで計画して、自分たちで知識を蓄えていって、しかも、すごくいいノリで外に発信するというようなものです。そういう自分の考えをもとに、僕は企業との連携で何かすることを提案したし、別の子は出張授業を提案してくれました。
――村上先生と松岡先生、Yさんを含めた学生数名が立ち上げメンバーとして集まり、いろんな提案が全部つながってコンセプトが定まったということですね。
Yさん 最初のミーティングで大枠の企画は決まって、それ以降で団長や階級、チームの構成を考えていきました。メンバーを募集するまでに3回ほど集まりました。
――メンバー募集の始める時には、何人ぐらい集まると想定していましたか?
Yさん いや、もう、ほとんど集まらないんじゃないかなと思っていました。
――それはなぜ?
Yさん 電気の学生たちって、自分たちで遊びに行ったりバイトしたりと、ゲームしたりと、プライベートを優先する人が多いと思っていたからです。だから、そういう文化祭的な活動に参加する人がいるのかな、と。予想では10人ぐらい集まったらいいかなって思っていました。
――実際には、40名近くの学生が集まったと聞いています。Sさんもそのうちの1人なんですよね?
Sさん そうです。
――Sさんは、HIT-ALPsに参加するまで、どんな学生生活を送っていたのですか?
Sさん 僕は高校までは人と話すのが苦手でしたが、作業的なことをするのは好きなほうでした。人のために動いて、かつ、ちょっと人と話もできたらいいなと思って、1年生の時はスペシャルオリンピックスという障がい者のスポーツイベントのボランティアに参加しました。2年生になっても人前で話すのが苦手だったので、ESSっていう、英語のスピーチを行うサークルに入って、話す練習をしていました。
――SさんはHIT-ALPsのメンバー募集の情報をどこで知ったのですか?
Sさん 一応、先生からアナウンスがありました。ざっくりと「電気の面白さを発信する活動をしたい」みたいな感じだったと思います。僕も時間が有り余ってたので、ちょうどよかったというか、とりあえずやってみようってことで友達を誘って参加しました。
――最初のミーティングに40人ぐらいの人が集まったんですよね。
Sさん 思ったより多くの人が集まったなと思いました。何かやって遊びたい人が多くて集まっていた感じです。
――じゃあ、やっぱりYさんの狙いは当たってたわけですね。もし勉強会とか言ってたら・・・
Sさん 勉強会だったら、参加してないですね。
――説明を聞いてどういう風に感じましたか。
Sさん 最初は半年間くらいのプロジェクトだと思っていたのですが、1年単位でやる活動だと説明を受けてちょっとびっくりしました。でも、せっかくなのでやってみようと、一緒に行った友達と入ることにしました。
――HIT-ALPsでは10チームに分かれて、それぞれがプロジェクトに取り組んでいるんですよね。お二人のチームではそれぞれ何に取り組んでいるのですか?
Yさん 僕のチームでは、自分で漕いだ自転車で発電するというアイデアの実験に取り組んでいました。
Sさん 僕は、リニアモーターカーやコンデンサーの仕組みを見せる小中学生向けの電気実験教室を行いました。
――実際やってみて、手応えはいかがでしたか?
Yさん 僕たちはオープンキャンパスで2回、体験コーナーさせていただいたんですけど、参加した高校生たちは楽しそうでした。体験後には高校生たちの進路相談にも対応しました。広島工業大学には、電気システム工学科と電子情報学科があるんですけど、どっちにしようか迷っているという子にはその説明もして、電気の就職状況を教えたら、じゃあ電気にしようかな、っていってくれた子もいましたね。
―― 実は電気って就職状況がかなりいいんですよね。
Yさん そうなんです。最初にこの活動を立ち上げる時にはそれほど深く考えていなかったのですが、高校生や小中学生、そしてその保護者に電気の面白さを伝えられたら、もっと電気を選ぶ人が増えるんじゃないかなって思います。
―― Sさんはいかがですか?
Sさん 僕は小中学生対象の教室なので、将来的に大学の学部選びにまでつながるかどうかわからないんですけど、喜んでくれる受講者は多くて、開催してよかったなと感じました。
――リニアモーターでものを動かすと子どもは喜びそうですもんね。
Sさん リニアモーターカーの仕組みを解説するために、1mくらいの短い距離ですが、電磁石などをちょっと配置して、簡単なキットみたいなのをつくって。詳しいことは理解できなかったかもしれませんが、動かしたら面白がってくれました。作ってる段階では伝わるのかどうか不安になったりしましたが、意外とウケました。
――それは、Sさんにとってはどんな体験になりましたか?
Sさん 小さい子どもが好きなので、「楽しい」の一言に尽きるかな。それに、ちょっと自信がつきました。この活動がどういうものか実感が湧いてなかったのですが、ちゃんと評価してもらえるんだなと思いました。
――計画段階では活動の狙いや意義が見えていなかったけれど、実際にやってみたら、目の前で喜んでくれる人がいて、活動を続けるモチベーションや、続けるための自信につながったということですね。
※肩書・掲載内容は取材当時(2024年12月)のものです。
【広島工業大学編】他の連載ページへ