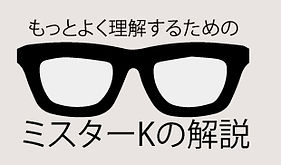連載4/「協同学習」で理系の対話力を育み、チームで学び合うキャリア教育を実践【大阪電気通信大学】
- odlabo
- 2025年11月10日
- 読了時間: 12分
更新日:2025年11月25日
今回の連載シリーズでは、2025年度から大阪電気通信大学で始まった「ジャンプスタート週間」における取り組みに注目。新入生の大学適応を促すために、複数の学科で弊社のチームビルディングプログラム『自己の探求』を導入していただき、それにまつわる方々にプログラムの体験談やその後の変化について話を伺ってきました。
連載の最後にご登場いただくのは同大でキャリア教育コンテンツの開発を担う、斉藤 幸一先生(教育開発推進センター 特任講師)です。日本語教育を専門とし、ライティング指導の経験豊富な斉藤先生は、理系学生のコミュニケーション課題に、「協同学習」の視点からアプローチしておられます。他者と共に学ぶという点において、チームビルディングと合い通じる部分も多い教育手法を用いておられる斉藤先生の目には、『自己の探求』はどのように映っているのか?プログラムを見学した感想やその後の学生の様子など、率直な思いを語っていただきました。
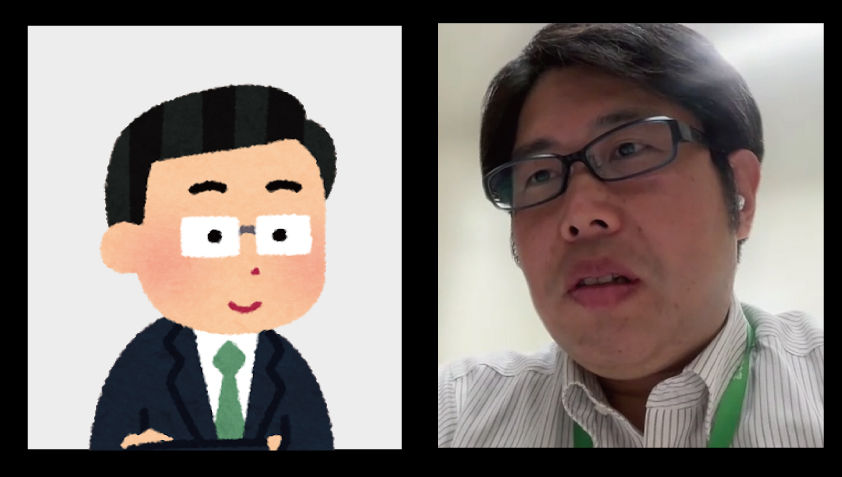
―― まずは斉藤先生のご経歴についてお伺いしたいのですが、ご専門とこれまでのキャリアについてお聞かせください。
斉藤先生 大学は文学部日本語日本文学科で、修士課程では日本語教育における「配慮表現」を研究していました。海外で日本語教師を務めた後、教員となり、2つの大学で学生のライティング能力強化の科目や学習支援ワークショップを担当していました。本学に着任したのは2020年です。本学の学生は理系の専門知識という強みを持つ一方で、対人コミュニケーションに課題を抱える学生も少なくありません。社会で必要となる基礎的なコミュニケーション能力を育成したいという大学のニーズに、私の言語コミュニケーション教育の経験が評価されたのではないかと思います。
――現在は主にどのようなことをされているのでしょうか。
斉藤先生 活動の柱はキャリア教育です。キャリアセンターと協働しながら、1年生から3年生までのキャリア教育のコンテンツを開発して、それを各学科に提供するという役割を担っています。私が作った教材を、学科の先生方に授業で活用していただくことが多いですね。
――教えていることは、前任校と大きくは変わらないのでしょうか?
斉藤先生 いえ、軸足は変わりました。以前はレポートの書き方など、個人の文章作成が中心でしたが、現在は「チームで動く」ことに主軸を置いています。私は前職で、チームで学び合うことによって相乗効果を生み出す手法を用いる「協同学習」に取り組んでいました。当時は、グループディスカッションなどを活用して文章能力を高めるという目的で使っていましたが、その手法を、彼ら自身がチームで動けるようになることを目的に、それを就職活動に応用している形です。
――学生と接する授業も担当されていますか?
斉藤先生 1年生から3年生まで、キャリア教育を担当しているクラスがあります。特に1年生と3年生のクラスには学科の先生と一緒に入り、ある意味モデルクラス的に授業を行っています。学科の先生から直接話を聞きながら、授業内容のブラッシュアップに取り組んでいます。
――自分の授業に他の教員が入ることに抵抗感を示す先生も多いと聞きますが、非常に先進的な取り組みですね。
斉藤先生 他大学では「餅は餅屋」でキャリアセンターに先生がいたら、その方にお任せしているのだと思いますが、本学では学科の先生にもキャリア教育に携わってもらいたいのだと思います。私自身も、前任校では職員の方々と一緒に授業を作っていた経験があるので、その延長線上にあると感じています 。
――学科の先生と一緒に授業を作るスタイルは、あまり聞かないですし、面白い取り組みですね。
では、ここから新入生オリエンテーションで弊社のチームビルディングプログラム『自己の探求』を導入していただいたことについてお伺いしたいと思います。2025年度より、従来のオリエンテーション期間を延長した「ジャンプスタート週間」が始まりました。これを機に、複数の学科でこのプログラムを導入していただきましたが、斉藤先生はこの件に携わっておられたのでしょうか。
斉藤先生 私自身は、すごく関わっているわけではありませんが、学務課の担当者から、機械工学科と基礎理工学科と情報学科に導入したいという話を聞いていました。基礎理工学科に関しては、1年生のキャリア教育も担当しているので、その子たちがどう変化していくのか知りたかったので、当日少し見学させていただいた程度です。
――プログラムについて事前にどのようなイメージを持っておられたのでしょうか?
斉藤先生 実施前に、動画で研修の様子は見させていただきました。また、ラーニングバリューの担当の方から、どのようなプログラムかについては事前に情報を得ていました。グループワークが性格的に合わない学生に対してはどのようにされるのかとか、チーム内でのフィードバックはどのように行われるのかについてはすごく興味がありました。
―― 実際にプログラムをご覧になった印象はいかがでしたか。
斉藤先生 私が見学したのは、学生がそれぞれ違う情報が書かれたカードを持ち寄り、すり合わせながら答えを探していくワークの最中でした。同じ基礎理工学科でも、3クラス間で雰囲気が全く違い、すごく賑やかなクラスもあれば、静かに淡々と進めているクラスもあって、その違いがとても面白く、印象に残っています。
――グループワークが苦手な学生への対応については、ご覧いただいてどのように感じられましたか?
斉藤先生 ラーニングバリューの担当者にも尋ねたのですが、基本的には学生本人と話をしながら進めることになり、参加を無理強いせず本人に決めてもらうように促す、と聞き、なるほどと納得しました。講師が本人とコミュニケーションを取って、本人の意思を尊重して進めてくださっていたと認識しています。
――プログラムを体験後、先生の授業に出席している学生に対して、例年と比べて何らかの違いは感じられますか?
斉藤先生 正直なところ、因果関係は分かりませんが、私の木曜1限の授業の出席率が、去年よりも低いという現象が起きています。ただ、他の先生に尋ねたところ、他のクラスでは学生同士が仲良くなって出席率が結構上がっているというので、プログラムとの因果関係は全然はわからず、なんとも言えないのですが・・・私の授業にはグループワークが苦手な学生が来ていないからかもしれませんが、授業自体はかなりやりやすいとは感じています。
――出席率やグループワークへの影響を評価するのは難しいのかもしれませんが、それでも斉藤先生が「授業をやりやすい」とおっしゃるのは、具体的にはどんなことを指しておられるのでしょうか?
斉藤先生 私が学科の先生と一緒に行っている授業では、大体4~5人でグループを組んで活動してもらうのですが、例年、メンバーの3人以上が参加しない、いわゆる「フリーライダー」が多数派になってしまうグループが出てしまうのですが、今年は今のところ、そういう事態にはなっていません。
――メンバーの組み合わせ方は例年同様ですか?
斉藤先生 はい。基本的に毎回メンバーを変えるため、出席率をもとにランダムに組み合わせて、グループも座席もこちらで指定しています。複数回連続して行う授業の場合は、同じグループでやってもらいます。
――来年度以降のも『自己の探求』を実施するとしたら、期待することはありますか。
斉藤先生 そうですね、これはラーニングバリューの方に教えていただいたのですが、先輩学生がファシリテーターなどの形で活躍できると、より良くなるだろうなと思います。身近な先輩というロールモデルがいることで、新入生も目指すべき姿が明確になり、モチベーションが上がる気がします。
――斉藤先生が担当されている授業で、今後の構想していることがあればお聞かせいただけますか。
斉藤先生 もう少し、基本的な力の育成に時間を割くべきかもしれない、と感じています。今回、いろんなこと、課外活動の先輩や大学の職員にインタビューして、チームでプレゼン資料を作るような活動をしているのですが、その土台となる読解力や考える力を育成するようなコンテンツにしてあげたほうがいいのかなと思っています。というのも、いきなりグループ活動をしようとしても、それらが不足していると、どうしても上滑りしてしまうおそれもあるからです。特に、生成AIの利用が当たり前になった今、AIが出してきた答えを鵜呑みにするのではなく、自分たちで意図を持って問いを立て、返ってきた答えをきちんと評価する。その上で、内容に責任を持ち、自分自身の言葉として他者に伝える。こうした一連のプロセス、つまり「自分の考えや相手の意見を正確に理解し、それを他の人へ伝える力」を、もっと伸ばせるようなプログラムがあったほうがいいと感じています。
――斉藤先生が学生のプレゼンを聞いても論理的思考が弱いように感じられるということでしょうか。
斉藤先生 コピペのようなものですよね。よくわかっていないが、レポートは勝手にできた、みたいな。でも、ちゃんと自分のつくったものに責任を持って、質問されても答えられるようになるのが大事なのではないでしょうか。それに、生成AIに対しての考え方やスキルはどこかできちんとやった方がいいのではないかとは思っています。
――授業の組み立ても難しいですし、グループ活動するにしてもコミュニケーション苦手な学生の割合が多いと先生方のご苦労も多いと思います。
斉藤先生 ある学科ではグループワークがないと聞いていたので、学生がチーム活動を受け入れてくれるのが心配していたのですが、きちんと取り組んでくれている学生が多くて。アンケートにも「人と話し合っていく中で視野が広がった」とか「気づきがあった」と書いてくれています。中には「話し合いする授業がこの授業ぐらいで、ちょっと楽しみです」という学生さんもいらっしゃって、そういう学生もある程度いるのかもしれません。授業のやり方次第なんでしょうね。
――斉藤先生の授業の方法について聞いてみたいことがあるのですが、「書く」という個人の活動を、「グループ」で行うことに、どのような教育的な意義があるとお考えなのでしょうか。
斉藤先生 協同教育の根幹にあるのは、グループでの成果自体が目的ではなく、あくまで個人の成長のためにグループを活用するという考え方です。もしかしたらチームビルディングのそれには反してしまうかもしれないですけども共に学ぶことで1番大事なところは個人の成長なんですね。文章を書くという行為も、その前段階にある「思考」が非常に重要になります。一人で思考するだけでなく、他者と対話することで思考を深め、その結果を文章に落とし込んでいくのです。授業で自分の考えをディスカッションし、そこでの気づきを自分の中に落とし込んで文章化する。このプロセスを通じて、一人では到達できなかったレベルの文章作成を目指すというようなことに取り組んでいます。
――キャリア教育においても、その対話を通じた学びを重視されているのですね。
斉藤先生 協同教育の手法は色々とあるんですけども、特に1年生の授業では、アカデミックスキルの1つに「話し合い学習法(LTD)」という手法を取り入れています。これは、キャリアを直接考えるというより、その手前にある「学ぶための基礎体力作り」が目的です。一つのテキストを各自が予習し、授業ではそれを元にディスカッションを行います。テキストの主張や話題を理解し、自分の知識と関連付けて言語化し、他者の意見を聞き、質問する。こうしたトレーニングを通じて、学ぶための基礎を築いていきます 。
――時間やルールの制限がありつつ、一人ひとりが発言する機会もあるとか、「話し合い学習法」って『自己の探求』と似ている点も多いなと思いました。
斉藤先生 そうですね。グループで話し合うことも、最後に振り返りをするのもすごく似てると思います。「この人の発言が良かったね」とか、「ここでもう少しこういう質問が出たら良かったかもしれない」など、お互いに振り返りながら、次の学びに生かせることを見つけ、より良い学び方につなげていくというような手法ですね。
――LTDのような学び方を通じて、どのような成長が期待できるとお考えですか?
斉藤先生 この学び方の良いところは、自分の予習が授業で活かされ、他者の役に立つという実感を得られる点です。自分の学びが誰かに貢献できる喜びを知ると、学生たちはもっと話し合いを充実させたいと、自主的に深く勉強するようになります。以前、あるクラスで、最初は全く発言できなかった学生が、3回目の授業で発言できるようになった時、周りのメンバーが心から喜んでいる姿を見たことがあります 。仲間の成長をみんなで喜べるような組織風土が、この学習法を通じて築かれていく。これは素晴らしい人間教育だと感じています 。
※肩書・掲載内容は取材当時(2025年7月)のものです。
【大阪電気通信大学編】他の連載ページへ

斉藤先生が取り組んでおられる話し合い学習法(LTD)は、学生の主体的な学びの習慣を育むのにとても面白い方法だと思います。斉藤先生のお話にあった通り、学生が小グループを作って一つのテキストを各自が予習し、授業ではそれを元にディスカッション形式で、テキストの主張や話題を理解し、自分の知識と関連付けて言語化し、他者の意見を聞いたり、質問したりしていく。こうしたトレーニングを通じて、読解力や表現力と言った学ぶための基礎を築いていく方法のようです。このような方法とチームビルディングはとても相性がいいのではないか、と感じています。斉藤先生のお話にも出てきたように、このような方法の課題の一つはフリーライダーの存在です。チームビルディングでは動機づけ(モチベーション)の基本的心理的欲求である「自律性」「有能感」「関係性」を、同時に、集団的に、刺激していくので、フリーライダーが生まれにくい構造になっています。チームビルディングとLTDを組み合わせた新たな学習方法を、斎藤先生と開発できたら面白いだろうなぁ、とお話を伺っていて感じました。