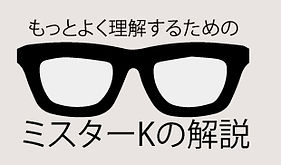連載1-1/大学適応を促す2週間の「ジャンプスタート週間」誕生の背景【大阪電気通信大学】
- odlabo
- 2025年8月25日
- 読了時間: 9分
更新日:2025年11月25日
大阪電気通信大学は、1941年に創設された東亜電気通信工学校にルーツを持ち、情報教育を出発点として、あらゆる学問に先進の情報テクノロジーを取り入れた教育を展開しておられる大学です。これまで記事で取り上げてきた多くの大学と同様に、同大学でも新入生の大学適応に課題を感じておられたそうです。そこで、2025年度より、授業開始をこれまでより1週間遅らせることを決断。新入生ガイダンスのあり方を抜本的に見直して、2週間の「ジャンプスタート週間」を設ける取り組みを始めておられます。学生が大学生活にスムーズに軟着陸するための準備期間の構想はいかにして生まれ、実現にこぎつけたのか。この取り組みの中心人物のひとりである学務部長の溝井浩先生(共通教育機構・数理科学教育研究センター 教授に、立ち上げの背景と新制度に込めた思いを聞いてみました。

――まず、溝井先生のご経歴とご専門についてお聞かせいただけますでしょうか。
溝井先生 専門は物理学です。物事の基本は物理学だろうと考え、理学部物理学科に入り、大学4年生で研究室に配属されて以来、ずっと原子核を主な研究テーマにしています。博士課程を修了後、理化学研究所などでポスドク(博士研究員)を経て、2004年に本学に着任しました。最近では、原子核物理学の知見を応用した非破壊装置開発など、少しずつ研究の幅も広がってきています。
――大学での現在のご所属は?
溝井先生 教員としての所属は、一般教養科目を担当する共通教育機構の数理科学教育研究センターです。ただ、今回ラーニングバリューさんとご縁ができたのは、僕が学務部の部長を務めているという立場が大きいです。
――大阪電気通信大学では、先生が事務系の部長職を兼任されるのですね。
溝井先生 学務部の各部署は、僕のような教員の部長と、事務方の実務を担う職員の事務部長との二人体制で運営しています。学務部は、かつての教務部と学生部が統合されてできた組織で、カリキュラムといった教育関係のことから、学生生活や課外活動の支援まで、学生に関わること全般を担っています。
――学務部長としての主な役割はどのようなことですが?
溝井先生 学務部長になったのは昨年ですが、その前は副部長として教務関係、主にカリキュラム改定の仕事を担当していました。部長になってからは、どちらかといえば学生生活を支援する業務の比重が大きくなっています。例えば、課外活動の支援や学生指導、そして今回お話しする『自己の探求』のような新しいプログラムの導入を検討・推進するのが、現在の僕の主な仕事です。
――まさに本日お聞きしたいのが、その『自己の探求』プログラム導入の経緯です。先生の目から見て、このプログラムはどのように導入されていったのでしょうか。
溝井先生 経緯としては、学務部事務部長の前任者であるFさんの存在が非常に大きいです。彼は御社とのお付き合いも長く、就職課にいた時代から『自己の探求』というプログラムを大学に導入したい、という構想をずっと温め続けていたそうです。
――はい、10年以上前からお世話になっております。
溝井先生 ただ、Fさんは事務方ですから、学生に対して何か新しいことを始めたくても、教員側の賛同者が見つからず、なかなか構想が前に進まない状況が続いていたようです。
そんな中、たまたま僕が学務部へ異動になり、Fさんと話す機会があって。彼からは、単なる教育という切り口ではなく、人間性を育むような観点から、入学したての学生たちの気持ちを盛り上げるプログラムをやりたいんだ、という熱い思いを聞いたんです。僕もその考えには非常に賛同したのですが、具体的にどの段階で、どうやって導入するかという点で、なかなか活路を見いだせず思案するような状況が続きました。
――導入には、どのような障壁があったのでしょうか。
溝井先生 まず、僕が特定の学科に所属していない、という立場的な難しさがありました。どこかの学科の教員であれば、「まず自分の学科で試してみます」ということも可能ですが、それもできません。よその学科に「こんなプログラムをやりませんか?」と持ちかけても、教員側から「うちの学生に余計なことをするな」という反応が返ってくることもありますから。
――なるほど、教員側の理解を得るのが難しい状況が続いたと。
溝井先生 それに、僕が学務部副部長だった頃の学務部長だったS先生は、そういうものに熱心に取り組んでおられたのですが、すでに他社のケースメソッドを用いたPBL(課題解決型学習)プログラムを取り入れておられたので、その上さらに『自己の探求』は必要なのだろうか、と言うお考えもありました。また、実際にやるとなると実施のための時間を確保しなければならず、その調整も大きな課題でした。いくつかの学科に少しずつ声をかけながら様子を見ていましたが、上記のような理由から、Fさんの構想はしばらく宙に浮いた状態が続いていたのです。
――停滞していた状況が動き出したきっかけは何だったのでしょうか。
溝井先生 転機になったのは、ベネッセさんのアセスメントテスト「GPSアカデミック」を全学的に導入しよう、という話が持ち上がり、新入生にも一斉に受験させることになったことです。様々なアイデアが集まってきたことで、「いっそのこと、入学式後のガイダンス期間を延長して、そこにいろいろな行事を詰め込んではどうか」という企画につながっていったのです。
――これまでは、新入生のガイダンスのためにどれくらいの期間を設けていたのですか?
溝井先生 ガイダンス期間は入学式後の約1週間で終え、すぐに授業を開始していました。今年度はその期間を思い切って2週間に延ばし、様々な取り組みを集中的に行う「ジャンプスタート週間」と位置づけることにしたのです。この新しい期間が確保できたことで、長年温めてきた『自己の探求』や、GPSアカデミックの受験が、ようやく実現できることになりました。
――新入生に焦点を当て、ガイダンス期間を延長し、行事を充実させたのは、どのような理由があるのでしょうか。
溝井先生 大きな目標は、学生の満足度を上げて、大学への定着率や愛着を高めることです。そのためには、やはり最初が肝心だと考えています。明確な調査結果があるわけではありませんが、学内の様々なアンケートや出席率のデータを分析していると、入学してからゴールデンウィークまでの過ごし方が、その後の4年間を大きく左右する、という雰囲気が感じられます。
――まさに「鉄は熱いうちに打て」と。
溝井先生 企業の新人研修が初期に集中的に行われるのも、同じ思想ですよね。ですので、まずは新入生を対象にしようと。Fさんは『自己の探求』を各学年で年度始めに繰り返し行い、その都度、気持ちを新たにするような仕組みを構想していたようですが、全学年に展開するほどの予算は確保できず、まずは1年生からということになりました。
――ちなみに「ジャンプスタート週間」を設ける前は、新入生オリエンテーションはどのように行われていたのですか?
溝井先生 本学の入学式は4月2日ですが、これまではそこから1週間でガイダンスを終え、すぐに授業をスタートさせていました。内容は、健康診断や履修登録の方法、学内での各種手続きの説明といった事務的なレクチャーが中心です。学生たちは、大学がどういう場所で、何を学ぶのか、よく知らないまま最初の授業に臨むことになっていました。
――準備が整わないまま授業がスタートしてしまっていたようだ、と。
溝井先生 そこからポロポロとこぼれ落ちていく1年生がいたのは事実です。教員の中には「それが大学だ。早く授業を始めることが大事だ」とおっしゃる方もいましたが、高校までとは全く違う大学という環境に慣れるための準備期間としては、あまりに短すぎるのではないか、という意見も以前からありました。特に、数年前から学生全員にノートパソコンを購入してもらい、授業に持参させることが必須になったのですが、その使い方に習熟しないまま授業が始まってしまう、という問題も起きていました。一部の学科からは、パソコンのセットアップや習熟のための期間を設けたいという要望も出ていました。そうした声も背景にあり、ガイダンス期間を2週間に延長し、そこに『自己の探求』やGPSアカデミックのようなプログラムを組み込むことで、学生たちが大学生活へスムーズに飛び乗れるような「ジャンプスタート週間」にしよう、というアイデアがまとまっていったのです。
――期間を倍に伸ばすことへの反対意見はなかったのですか?
溝井先生 もちろんありました。「だらだらと準備に時間をかけるうちに、逆に学生の熱意が冷めてしまうのではないか」といった懸念の声もありました。しかし、今年やってみて、結果的に準備期間を十分に取れたことは、1年生にとって非常に良かったと感じています。最初の一週間は従来通りのガイダンスを行い、次の一週間でその内容を実体験したり、仲間づくりをしたりする時間ができたことで、学生は大学により馴染みやすくなったのではないでしょうか。特に『自己の探求』を実施した学科の学生は、そう感じていると思います。
――授業開始が1週間遅れることは、上級生にも影響しますよね?
溝井先生 はい、もちろんそれも問題視されました。「上級生はやることがなくてダメになるじゃないか」とおっしゃる先生も多かったのですが、新入生の歓迎イベントを上級生に企画・運営してもらったり、課外活動の紹介をしてもらったりするなど、彼らの活動の機会も用意したんです。GPSアカデミックの受験は全学年で実施することにしたので、それも受験してもらいましたしね。あと、学科のグループ担任と面談する機会も設けてもらいました。
――貴学にはグループ担任の制度があるんですね。
溝井先生 本学には全学科でグループ担任制度があり、教員一人が各学年10人程度の学生を卒業研究の研究室が決まるまで担当することになっています。新入生は入学時点で担任と面談する機会をつくるのですが、これまで上級生はほったらかしだったんです。今年度は上級生もグループ担任との面談を行ってもらいました。特に、単位が足りず留年しそうな学生に対して、この一年をどう履修し、どう学んでいけばうまくいくかといった個別の丁寧なケアを行う良い機会になったと思います。
――上級生にとってもよい準備期間になったようですね。
溝井先生 単に春休みが1週間延びたと捉えるのではなく、下級生の面倒を見たり、自分自身の学びについて考えたりと、大学が単に勉強するだけの場所ではなく、人間関係を築く場所でもある、と理解してくれた学生も多かったようです。中には、できた時間を使って海外に行くなど、活動の幅を広げる学生もいました。上級生にとっても、決して悪いことではなかったと考えています。
※肩書・掲載内容は取材当時(2025年7月)のものです。
【大阪電気通信大学編】他の連載ページへ