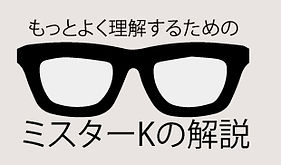連載2/自信がない学生に「できる」体験を。自分で選んだ仲間とグループワークに臨む【大阪電気通信大学】
- odlabo
- 2025年10月10日
- 読了時間: 11分
更新日:2025年11月25日
大阪電気通信大学では、新入生が落ち着いて学ぶ態勢を整えられる準備期間として、2025年度より2週間の「ジャンプスタート週間」を設けておられます。新入生ガイダンスの抜本的な見直しを行い、授業開始をこれまでより1週間遅らせて、学科単位で大学適応をスムーズにするためのさまざまな取り組みが行われました。その中で、3つの学科で弊社のチームビルディングプログラム『自己の探求』を実施していただきました。なぜ今、このようなプログラムが必要だと思われたのか。『自己の探求』2日版を導入していただいた情報学科の学科主任の升谷 保博先生(総合情報学部 情報学科 教授)に、導入の背景や、当日あるいはその後の学生の様子を見て感じたことについてお聞かせいただきました。

――まずは簡単に升谷先生のご経歴をお伺いできますでしょうか?先生は大学から情報を学んでおられたんですか?
升谷先生 いえ、実は大学生のときはロボットをやりたくて、大阪大学の基礎工学部機械工学科に入学しました。大学院でもロボットの研究をしていたのですが、研究でコンピューターやプログラミングに触れるうちに、だんだんそちらの方に力が入っていきまして。そのまま母校で助手、助教授を務めていたのですが、ちょうど20年前に本学(大阪電気通信大学)が新しく情報系の学科をつくるというタイミングで、研究室の先輩に声をかけていただき、こちらに移ってきました。それ以来、情報系の教員として学生の指導にあたっています。
――新入生のガイダンス期間にあたる「ジャンプスタート週間」に、弊社のチームビルディングプログラム『自己の探求』を実施していただいたのですが、導入の背景についてお聞かせください。
升谷先生 直接のきっかけは、学務課の職員の方から「こういうプログラムがあるけど、やってみませんか?」と声をかけていただいたことです。大学全体で導入する前に、いくつかの学科で試行したいという話でした。学科内には「そんな研修に意味があるのか?」という懐疑的な声もありましたが、私は割と何でもやってみたいと思う方なので。「とりあえず試してみたらいいじゃないか」と、当時学科主任だった私が押し切る形で導入を決めました。
――それまでは、新入生向けの行事はどのようにされていたのですか?
升谷先生 コロナ前は、学科独自の判断で新入生向けの学外研修を毎年実施していました。大学から予算の補助が出る制度があり、私たちはそれを使って、自分たちが授業で使うノートパソコンの製造工場や、スーパーコンピュータの施設などを見学する1泊2日の研修を行っていました。見学だけでなく、夜や翌日にワークショップを実施して、新入生同士や教員との交流を深めるのが目的です。しかし、コロナ禍で中断し、昨年復活させたものの、教員側の負担が非常に大きいという課題がありました。
――具体的に、どのような点が大変だったのでしょうか。
升谷先生 移動や宿泊、見学先の手配などをすべて教員が行わなければなりませんし、ワークショップにしても、本当にうまくいっているのか、という不安は常にありました。また、見学先の都合で、5月の連休明けに実施していたのですが、本当は入学直後に学生同士が仲良くなる機会が必要だと感じていました。そうした中で、オリエンテーション期間中にプロの方にチームビルディングプログラムを実施していただく、という今回の提案は非常に魅力的でした。
――特にプログラムに期待されていたことはありますか?
升谷先生 私たちが学生をグループに分けて何らかのワークをしてもらおうとすると、輪に入れなかったり、うまく協働できなかったりする学生が出てきてしまう、ということがよくありました。自分たちではうまくやれていない、という感覚があったので、プロのファシリテーターはどういう風に進めるのだろう、という興味がありました。
タイミングも良かったんです。本学は今年度から授業開始を1週間遅らせ、「ジャンプスタート週間」を設けることになりました。オリエンテーション期間が長くなったので、その時期にそういうプログラムをはめ込んで、しかもプロの方にやっていただいたらどうだろうかとも考えました。お手並み拝見、というと失礼かもしれませんが、純粋に楽しみにしていましたね。
――ご覧になられての感想はいかがでしたか?
升谷先生 いや、本当に上手に進められるな、と感心しました。事前に不安だったことが2つあるのですが、1つは「グループ分けがうまくできるか」。もう1つは「一度決めたグループで2日間も活動が続くのか」という点でした。
私たちがやっていた研修でもグループづくりに苦労して、こちらが指示してもなかなかメンバーが決まらなかったり、輪に入れない学生が出たりしていました。苦肉の策で、机を12の班に分けて「誕生月で集まって」とやったこともあります。
ところが今回は、非常に巧みに誘導されるな、と。まず個々で自分のことを分析する段階があり、その結果がレーダーチャートで示されます。そして、「そのチャートの形ができるだけ違う人とチームを組んでください」という明確な指示がありました。それ以外にも、同じ高校出身者や女子学生だけで固まらないように、といった配慮もありましたね。
――「あなたの学習スタイル」というツールを用いて、学生が自分の学習スタイルを可視化し、それを元に自分たちでグループ分けを行う実習ですね。学生たちの反応はいかがでしたか?
升谷先生 ファシリテーターの方は強く指示するのではなく、「自分たちでやってください」というスタンスでしたが、学生たちはその指示に素直に従い、チャートを見比べながら割とすんなりとグループを決めていました。単に「集まれ」と指示するだけではダメで、「なぜそうするのか」という目的や考え方を示す、多様な人が集まることの意味を伝える、といった仕掛けがあるからうまくいくのだな、と。これは本当に驚きでしたし、うまいなと感心しました。
――先生の指示でできたグループが気に入らなければ、その不満は先生に向かってきます。このプログラムでは、考え方だけ示して、自分たちで決めてもらうんですよね。「多様な人が集まる方がいいみたいだから、それでやってみよう」と言われて納得して、自分たちで決めてもらう。ですから、このグループが嫌だというような動きはほぼ出てきません。ファシリテーターも、「何のためにやるか」を伝えるよう意識しています。
升谷先生 なるほど。だから、なぜこういうことをするのかとか、こういう考えがあるという説明をしながら進めてくださったんですね。
――もう一つの不安点、二日間同じメンバーで活動できるのか、という点はいかがでしたか?
升谷先生 それも、案外できているんですよね。二日目に若干名の欠席や早退者もいましたが、最後まで参加した学生たちは、最後のメッセージ交換なども非常にいい雰囲気でやっていました。思ったよりもみんな話せるし、発言できる。うまく仕掛けてあげれば、彼らはちゃんとやれるようになるんだな、という手応えを感じましたね。良かったんじゃないかと思います。
――プログラムを終えて少し時間が経ちましたが、先生の実感として、今年の新入生に例年と比べて何か変化は感じられますか?
升谷先生 正直なところ、私自身は明確な違いまでは分かりません。1年生の授業を多く担当している他の先生に聞くと、「なんとなく元気な学生が多い気がする」「よく喋る学生が多いようだ」といった声も聞かれます。ただ、それがたまたま今年の学生の個性なのか、このプログラムのおかげなのかは、はっきりとは分からないですね。「特別大きな違いは感じない」というのが、多くの教員の感想かもしれません。ご期待に添える答えになっていないかもしれませんが。
――いえいえ。初めての実施でしたし、前年度との単純比較は難しいですよね。
升谷先生 効果を測ることの難しさは感じています。そもそも、学生の様子は年度によってかなり違いがあります。例えば、毎年1年生の6月頃にプログラミングの簡単な中間試験を行うのですが、その成績分布は年度によって全く違うんです。全体的に良い年もあれば、低い方に固まる年、成績が良い層と悪い層の2つの山ができる年など、様々です。もともとそれだけの差がある中で、今回の研修が与えた影響だけを正確に見極めるのは難しいな、と。
――プログラムの影響なのか、その学年の特徴なのか、断定できないということですね。
升谷先生 もちろん、何らかの効果はあったと信じています。大学の勉強では、学生同士で教え合ったり、励まし合ったりすることが非常に重要です。しかし、授業には出てきているものの、いつも一人で講義を受けているような学生も一定数います。今回の研修が、学生たちがお互いに協力して学んだり、共に成長したりする雰囲気をつくるきっかけになってくれれば、と期待しています。
―それではプログラムの内容や進め方について、他の先生方の反応はいかがでしたか?
升谷先生 ファシリテーターの方々のスキルの高さには、多くの教員が感心していましたね。ファシリテーターの方が、ご自身の経験談や巧みな例え話を挟みながら、学生の興味を引きつけていたことですね。例えば、「ドラえもんのキャラクターで言うと、このタイプは誰々だよね」とか、「ONE PIECEならこのキャラクターかな」といった、学生に身近な例えを使ったり、ご自身が社会人だった頃の話をされたり。プロですから当然なのかもしれませんが、学生を飽きさせず、うまく巻き込んでいく手腕は「さすがだな」と思いました。
――升谷先生がご覧になった範囲でよいのですが、今回のプログラムは学生たちにとって、どのような時間になったと思われますか?
升谷先生 新入生というのは、大学の教室という新しい環境で、自分がどう振る舞えばいいのか分からず、迷っている状態だと思うんです。友人関係やクラスメートとの付き合い方をどう築いていくか。今回のプログラムは、グループワークなどを通じて、そうした人間関係のつくり方をいろいろと「試す」機会になったのではないでしょうか。もしこうした機会がまったくなく、いきなり授業が始まっていたら、何も試せないまま4年間がスタートしてしまったかもしれません。
――今おっしゃった「学生がいろいろ試す」というのは、非常に面白い視点ですね。最近よく言われる「心理的安全性」は、誰かが一方的に用意するものではなく、学生自身が試行錯誤しながら自分たちでつくっていくものなのかもしれません。
升谷先生ご自身は、今回の取り組みを、今後どのように学科運営につなげたり発展させたりしていきたいとお考えですか?
升谷先生 本学では新入生を学籍番号順に10数人ずつのグループに分けて、担当教員がつく「グループ担任制」を導入しています。これまでも授業開始前に自分の担当学生を集めて、グループでアイスブレイクを行ったり、LINE交換を促したりする程度のことはしていましたが、それだけでした。今回のように、2日間かけてじっくりと関係構築に取り組むのは初めての試みでしたが、今後も続けていけばよいのではないかと思っています。
そういえば、他大学では、前年度にこのプログラムを経験した2年生が、サポート役として新入生のクラスに入るという活用法もあると聞きました。本学では、新入生のサポートを大学院生に手伝ってもらうことはあっても、すぐ上の学年の学生が関わるような行事はほとんどありませんでした。上級生と下級生が交わる機会をつくるという意味でも、試してみてもいいのではないかと思いました。
あと、私たち教員も「ぜひ、先生方だけのグループをつくって、学生の横で同じワークをやってみませんか」とご提案いただいたのですが、今回は教員各々が折を見て様子を見に行くだけになってしまいました。もし、ある時間は教員もグループに参加して、学生とやり取りする時間があるとか、プログラムの中に学生と教員の距離を縮められるような仕掛けがあれば、さらに良かったのかもしれませんね。
※肩書・掲載内容は取材当時(2025年7月)のものです。
【大阪電気通信大学編】他の連載ページへ

今回のプログラムは、グループワークなどを通じて、人間関係のつくり方を学生らがいろいろと「試す」機会になったのではないか。升谷先生の視点は正にその通りだと感じました。みなさんの大学では、そのような機会をどのように用意されているのでしょうか。新入生のオリエンテーション期間、多くの大学では、様々なプログラムを用意されていらっしゃいます。たとえば「友達作りのプログラム」や「履修登録の方法」「各窓口の活用の仕方」などなど、各部署が工夫しながら少しでも学生の理解が進むように苦労されています。一方で、それぞれの繋がりをどう設計するか、それらを通して学生の人間関係がどのように進んで行くか、などを意図しているところは少ないのではないでしょうか。
チームビルディングプログラムを設計する上で最も重要なことは、どのような流れになるかと言うことではないかと考えています。それはプログラムの構成上だけでなく、前後にどのようなイベントが用意され、学生らがどのような体験をするのか、その流れの中でチームビルディングプログラムがどのように機能することを期待するのか、と言うことも含めてです。とりわけ入学直後の流れは、その後の学生らの大学適応にとても大きな影響を持っているように思います。学生それぞれが、それぞれのペースで人間関係を試す機会を作る。大阪電気通信大学様のジャンプスタート週間がそのように発展していくことを願ってやみません。