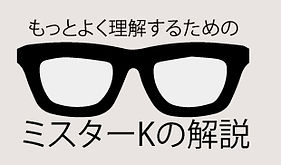連載1-2/関係性は深まった。次なる課題は「学び合い」への転換【大阪電気通信大学】
- odlabo
- 2025年9月10日
- 読了時間: 9分
更新日:2025年11月25日
新入生ガイダンスのあり方を抜本的に見直した大阪電気通信大学。新入生が大学生活にスムーズに軟着陸するようにと、2025年度から2週間の「ジャンプスタート週間」を設けています。準備期間を2週間に延長したことで、アセスメントテストやPCセットアップのほか、各学科による親睦行事なども余裕をもって実施できるようになったそうです。学科別企画の一部として、3学科では弊社のチームビルディングプログラム『自己の探求』も導入させていただきました。例年にない試みを終え、学生にはどのような変化が起きているのか?新入生ガイダンスのリニューアルがもたらした具体的な変化や、その先に見えてきた新たな課題とは何か。学務部長の溝井浩先生(共通教育機構・数理科学教育研究センター 教授)に聞かせていただきました。

――様々なハードルを乗り越えて、『自己の探求』を導入いただきましたが、溝井先生は当日の様子もご覧になったのでしょうか?
溝井先生 はい。実施された3学科のうち、1日版を実施した2学科の学生の様子はずっと見ていました。
――当日の様子をご覧になっての率直なご感想をお聞かせください。
溝井先生 事前にプログラムの内容は聞いていたのですが、導入するにあたって各学科の先生方との事前打ち合わせの場で非常に多く言われたのが、「こんなことは小学校や中学校でずっとやってきたことじゃないか」「今さら、なぜこんなことにお金をかけるんだ?」という懐疑的な意見でした。アイスブレイク的な自己紹介や簡単なグループワークで仲良くなりましょうといった試みは、これまでに何度も経験しているはずだ、と。
――先生方からすれば、目新しさがないように見えたのですね。
溝井先生 そうだと思います。僕自身は、このプログラムの導入に積極的だったFさん(前学務部事務部長)たちから事前に詳しい話を聞いていたので、そんなに浅いものではないだろうと理解はしていました。ただ、学生とプログラムのファシリテーターの方々の間で、具体的にどのようなやり取りが行われ、どういう深さで進んでいくのかはまったく想像できなかったので、「プロの技を盗んでやろう」という気持ちで見学させていただきました。
――日頃から教壇に立っておられる先生としての視点からご覧になって、いかがでしたか?
溝井先生 「やはりプロは違うな」と感心しましたね。学生たちは事前に何をするか知らされずに参加しているので、最初は「なんでこんなことをやらされるんだ」という顔をしていました。その彼らの心をどう掴み、プログラムに気持ちを向けさせるのかと思っていましたが、自己紹介一つとっても、我々とはまったく違う切り口で、学生の心を掴むような面白い導入をされていました。僕たちだったら、「今日はこういう作業をこんな感じで進行します」っていう機械的な説明になっちゃうんですけども、その日の過ごし方に期待が持てるようなイントロダクションになっていて。学生たちも、なんだろうこれは?という興味をそそられたような顔をしてました。それに、プログラムの最中も、僕たち教員であれば、学生が困っているとつい手を出して手伝ってしまうような場面でも、じっと待つとか。我々も授業の最初には、どうやって学生の目をこちらに向けさせるかは常に考えていることなので、その観点で非常に勉強になりました。
――進行の仕方で印象に残っていることはありますか?
溝井先生 3つの教室で同時にプログラムを実施していましたが、それぞれの教室の進行がまったく違ったことです。我々が同じようなことをやると、どうしても他の教室と進行を合わせようという意識が働いてしまいます。しかし、講師の方々は他の教室の進行状況などお構いなしに、それぞれの教室にいる学生たちの特性を瞬時に見抜き、柔軟に進行を組み立てていました。そのあたりは、本当にすごいなと思いました。
――その教室の学生の状況を見ながら、彼らのスピードに合わせてプログラムを進行するようにファシリテーターに委ねられているので、同じことをやっているように見えて、各教室の動きはまったく異なって見えたのかもしれませんね。
溝井先生 最初に、ネームカードのようなものをお互いに書き合い、プロフィールを交換しながら話し合う「記者会見」というワークがありました。その時、学生たちが本当に素直に、スッとプログラムに乗ってくれたのが印象的でした。正直、僕たちが同じことをやっても、あんなにスムーズに学生は動かないのではないかと思います。最初の導入と、この最初のグループワークで、学生同士の距離がぐっと近づいたのを感じましたね。
私が見学したのは、工学部の機械工学科と、基礎理工学科ですが、学科によって学生の特性が違うので、学生の反応が異なっているのも興味深かったです。
――具体的には、どのように違ったのでしょうか。
溝井先生 機械工学科は、機械系を学びたいという目的意識がはっきりした学生が多く、専門性に対する意欲も高い。そのためか、プログラムの意義を比較的早い段階で理解し、積極的に参加していたように見えました。一方の基礎理工学科には志望動機が明確でない学生もいて、入学時点でのモチベーションにばらつきがあります。そのためか、立ち上がりは少し遅いように感じました。ただ、ファシリテーターの方々が上手に引き上げてくれて、午前中が終わる頃には、機械工学科と同じくらいいい雰囲気になっていました。
――プログラムを実施して2ヶ月ほど経ちましたが、学生たちの様子に変化は感じられますか?
溝井先生 僕が見学した2学科に関して言えば、現段階では例年より大学生活を楽しんでくれているように感じています。
――どのような場面で、そう感じられますか?
溝井先生 例えば、実験やグループでの作業をしている時です。これまでは、作業が遅い学生がいると、周りがイライラして「早くやれ」という雰囲気になったり、全く会話が無くなったりすることがよくありました。しかし今年は、そうした光景をあまり見かけません。むしろ、遅れている子がいたら、周りが自然に手伝ってあげる。人付き合いの心理的なバリアが、明らかに下がっていると感じます。学力が特に高まったということはありませんが、明らかに大学という場所や、そこでできた友達・仲間を好きになってくれているのを強く感じます。逆に、今年は仲良くなりすぎて授業中にうるさい、という話はよく聞きますね(笑)。
――それは、私どももよく言われます(笑)。ポジティブな変化がある一方で、何か課題も見えてきていますか?
溝井先生 一番の懸念は、「みんな横を見ながら、みんなで一緒に沈んでいく」ことにならないか、という点です。学期末を迎えて「みんなで落ちれば怖くない」といった雰囲気が少しずつ出てきているのではないかと気がかりです。仲が良いのは素晴らしいことですが、やはり学業で結果を残してもらわなければなりません。良い意味で、お互いに勉強会を開いて「もっと良い点を取ろう」と高め合っているグループもできつつあるのですが、そうでないグループとの二極化が進んでいるようにも見え、そこは心配ですね。
――関係性ができたからこその、次の課題かもしれませんね。少し参考になるかもしれないので、私がお手伝いしている医療系大学の事例をご紹介させていただいてもいいでしょうか。そこは国家資格取得が必須の大学ですが、入試科目に数学がない学科もあり、学生の数的処理能力にばらつきがあるという課題を抱えていました。
そこで、全学共通の基盤教育のある科目にチームビルディングを取り入れることにしたんです。5つの学科の学生を混ぜた混合グループを作り、初年次の授業の最初の数回でチームビルディングを行います。使うコンテンツは弊社が提供し、先生方にファシリテーションを学んでいただいた上で、授業を進めてもらう形をとっています。その後、SPI(適性検査)の非言語分野の問題集を使い、チームで課題に取り組んでもらうのです。授業の最初にミニテスト、授業内で教え合い、最後にポストテストを実施し、チームの合計点の伸びを競い合う。そうすると、個人成績は開示されませんが、チームのために頑張るという動機が生まれ、自然な学び合いが促進されます。
さらに、この取り組みは先生方にも良い影響があります。同じ教材を使いながらも、クラスごとに進め方は様々です。授業後に先生方が集まっていただき「うちのクラスはこのように進めた」と振り返りを行うことで、先生同士のチームビルディングも進んでいく、という副産物もあるんです。チームビルディングプログラムは、課題に応じてさまざまに設計できますので、今後も情報交換をさせていただきながら、何かお手伝いできればと思います。
さて、少し視点を戻して、「ジャンプスタート週間」のその後についてもお伺いしたいと思います。ガイダンスの見直しによって、春以降、何か目に見える変化はありましたか?
溝井先生 はい。この改革のおかげか、今年は例年に比べて授業の出席率がかなり良いです。これは新入生だけでなく、全学年で見られる傾向です。やはり、年度の初めに準備期間が十分にあったことが、良い影響を与えたのではないかと評価しています。
――素晴らしいですね。導入前は反対意見も多かったとのことですが、来年度もこの形は継続されるのですよね。
溝井先生 そうですね。今、来年度の学事日程を作成しているところですが、カレンダー上は、入学式から2週間程度の準備期間を確保する想定で進めています。今は今年実施した『自己の探求』やGPSアカデミック、グループ担任面談などがどうだったか、効果検証を行っている最中です。その結果を踏まえて来年度の中身を検討するつもりです。
――現時点での、学内での評価はいかがですか?
溝井先生 ネガティブな意見は、今のところ全く聞こえてきません。昨年の今頃、この話を始めた時は「授業開始を1週間も遅らせて一体何をするんだ」と大変でしたが、力ずくで進めた部分もあります(笑)。でも、いざ蓋を開けてみたら、「のんびりできて良かった」という声が多いですね。実は、年度始めは教員も非常に忙しいので、準備期間ができて助かった、という側面もあったようです。
――なるほど。結果的に、皆さんにとって良かったのですね。
溝井先生 はい。今となっては「元に戻そう」という話はまったくありません。今年の内容を積極的に評価する声が大きく上がっているわけではありませんが、否定的な意見が出ないというのは、この改革が受け入れられた証拠なのかもしれません。
※肩書・掲載内容は取材当時(2025年7月)のものです。
【大阪電気通信大学編】他の連載ページへ