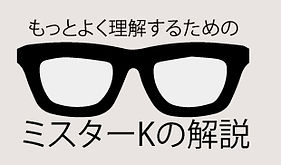連載5/「電気の魅力発信」学生プロジェクトの裏側~SNSチームの奮闘記【広島工業大学】
- odlabo
- 2025年7月25日
- 読了時間: 12分
更新日:2025年8月4日
広島工業大学 電気システム工学科では2024年から、学生が主体となって学科の魅力を発信するプロジェクト「HIT-ALPs」が進行しています。教員からの誘いをきっかけに参加したTさん(取材当時2年生)は、プロジェクトに参加しつつ、活動全体を広報するSNS担当に立候補。動画編集の経験を活かし、現在はSNSチームのリーダーを務めています。SNSチーム立ち上げの経緯や具体的な活動内容、チーム運営の苦労ややりがい、そして今後の展望について語ってもらいました。

工学部電気システム工学科2年・Tさん(山口県出身。地元の工業高校電子機械科を卒業後、さらに電気の知識を学ぶべく「地元に近く、中四国エリアで就職に強い大学だから」と広島工業大学に進学。HIT-ALPs に参加し、SNSチームのリーダーを務める)
――今回はHIT-ALPsの話を中心に聞きたいと思っています。まずは、Tさんが活動に参加することになったきっかけを教えてください。
Tさん 2024年2月頃に、電気システム工学科の村上先生からメールが来て、「新しいプロジェクトをつくるから、ちょっと話をだけでも聞いてみないか」みたいなことを言われて。「3、4年生は集まったんだけど、2年生もいっぱい集まってほしいから、Tくんは元気がいいからぜひ入ってほしい」って誘われたんです。
――プロジェクトメンバーの一期生は40人くらいいたんですよね?
Tさん はい、もっと小規模な感じでやるなるようなイメージだったので意外な気がしました。先輩方もいらっしゃったけど、同級生が多かったので、みんなこういうの参加するんだ、ってちょっと不思議な気がしたのを覚えています。
――プロジェクトの詳細についてはその時に初めて聞いたのですか。
Tさん そうですね。教室で村上先生と松岡先生と学園祭実行委員の経験もあるYさんから説明を聞きました。「電気の入学者が少ないから、もっと電気って面白ってことを発信するんだ」っていう意図はわかったんですよ。だけど、どうやってやるの?自分たちで考えてやれるのかな?と思いました。ただ、ゼロから立ち上げる新しいプロジェクトをやるっていうのはわかったんで、僕も経験したいって思いました。
――HIT-ALPsは、10のチームに分かれてプロジェクトに行っていたと聞いていますが、どのようにチーム分けをしたのですか?
Tさん 最初は知らない人が多かったので、身近な仲の良い2年生3人ぐらいでチームをつくって。そこに3、4年生の先輩が1、2人加わる形で、4~5人のチームが10個できました。その後、1年生が入学後に参加してくれて、最終的に10人ずつくらいのチームになりました。
―― 結構大きなチームですね。1年生メンバーはどのようにして加わってくれたのですか?
Tさん 1年生のオリゼミ(オリエンテーションゼミ)があって、そこにHIT-ALPsの学生が指導役として入ったんです。その時に僕たちが担当した1年生の子たちが、「T先輩知ってるし」という感じで入ってくれました。
――Tさんのチームのプロジェクトの方はどんな内容ですか?
Tさん 「卵ランプ」づくりです。風船に毛糸を巻き付けてボンドで固め、風船を割ると毛糸の球体が残ります。それに下からライトを当てると綺麗なので、それを作る工作体験をしようというプロジェクトです。
―― なるほど、インテリア工作ですね。
Tさん 最初は講演会なども考えたのですが、他のチームも似たような企画を考えていたので、工作体験の方が良いだろうということになりました。今は、2月半ばに大学近くの坪井公民館で行われるイベントに、初めてチームで出店できるように動いている段階です。工作に興味があるのは、小学生メインで、中学生も参加OKという感じのイベントです。
――TさんはSNSチームのリーダーだそうですが、それは10のプロジェクトチームとは別のチームなんですか?
Tさん はい、別です。10のチームの活動を宣伝するためにできた、言うなれば「11個目のチーム」で、僕は掛け持ちでやっています。
―― SNSで宣伝することになったきっけかは?
Tさん 2月にみんなで集まった時に、「何か発信するものはいるよね」となって動き出しました。3月に会議を重ねて、XやYouTubeなど媒体を検討した結果、「画像もテキストも扱えるし、リール動画も投稿できるから」とInstagramに決定。YouTubeだと高度な編集技術も必要になるので、現状ではInstagramが一番合っていると考えています。3月末にアカウントを開設しました。立ち上げメンバーは3人で、準備に1ヶ月半ぐらいかかりましたね。
―― TさんはなぜSNSチームに参加することになったのですか?
Tさん 高校の時から趣味で、スマホアプリの「Cap Cut」を使って動画編集をやっていたんです。部活の様子を撮って、字幕やBGM、効果音を入れたりしていました。YouTubeに流れてくるような洗練されたものではないですが、一通りの編集はできるレベルでした。放課後に遊んだ時の動画を撮って、思い出として後で見返せるようにしてました。最初は自己満足で始めたんですが、部活のグループLINEにも日々の様子をアップするようになりました。
―― ちょっとした動画監督ですね!その経験があったから手を挙げられたのですね。Instagramではどんなことを発信しているのですか?
Tさん 主に、HIT-ALPsの10チームがそれぞれどんな活動をしているかの紹介です。HIT-ALPsに限らず電気システム工学科の魅力を発信すること
が目的なので、学科としてこういうことをしている、という内容も発信した方が良いと考えています。授業風景などを紹介するのもその一環です。
―― 扱うコンテンツを学科全体に広げていったのですね。
Tさん 広げていったというか、正直、投稿ネタが少しなくなってきたという事情もあります。そこで、少し電気とは離れますが、扱う範囲を広げて、大学周辺のおすすめのお店情報なども投稿するようになりました。
―― フォロワーの内訳はある程度わかっているのでしょうか? 電気システム工学科に興味を持ってくれる人にリーチしたいという目論見もあったようですが、高校生など、ターゲット層は増えている感触はありますか?
Tさん 感覚ですが、半数以上はうちの学科の学生だと思います。最初にバーッと増えたのは、「インスタ始めたから登録しろよ」という感じで学内の学生が増えたからです。外部の方は、オープンキャンパスで興味を持ってくれた高校生にQRコード付きの資料を配ってフォローしてもらったり、学科と関わりのある企業の方がフォローしてくださったり、先生のつながりでOBの方がフォローしてくださったり、という感じで、合わせて40人くらいでしょうか。なので、外部の方はまだ少ないですね。
――フォロワーを増やすために、コンテンツの見直しなどはされていますか?
Tさん 他の大学のインスタを参考にして、「日常系の動画が良いのでは」という意見は出ました。ただ、女子大生がピースしている動画は可愛くて伸びるかもしれないけれど、男子学生がやっても伸びるのかな、という疑問もあったりして。とはいえ、試しに、セミが鳴いているような夏の風景動画のようなものを上げてみたんですが、案外いいなと思って。電気はどうしても堅苦しいイメージがあるのでそういう日常の様子を上げるようなものも考えていきたいですね。「大学の先生の休日の過ごし方」みたいなものも試しに投稿してみました。「大学の教授って普段何してるんだろう?」という視点で、村上先生が宮島に行った写真や、松岡先生のお気に入りの金沢カレーを楽しめるスポットを紹介する投稿などです。
――カレーの投稿、反響はどうでしたか?
Tさん 「16イイネ」がでした。このアカウントの投稿の中では多い方ですよ。こういった変わった視点からのネタも試行錯誤しながらやっています。
――いろいろと工夫されているようですが、手応えはいかがですか?
Tさん 正直、最近は伸び悩んでいるなと感じています。フォロワー数が今188人(2024年12月時点)なのですが、以前一気に140~150人くらいまで増えた後、そこからが伸び悩んでいます。授業が忙しくなって投稿頻度が10月以降、週1回くらいに落ちてしまっているのも原因だと思います。元々は週2~3回は上げたいと思っていたのですが…
―― 週1回でも十分な頻度だと思いますよ。活動で苦労しているのはどんなことですか?
Tさん 個人的には、編集時間の確保に苦労しています。授業やバイトもある中、どこで編集時間を捻出するか。案の定、最近は全然編集できていなくて…。これから冬休みなので、そこで一気に編集してストックを作って投稿しようと思っています。これは意気込みですが(笑)。
あとは、各プロジェクトチームからのネタ集めですね。共有フォルダに「何日までにインスタのネタを投稿してください」と依頼するのですが、期限を守ってくれないチームもあって(苦笑)。宿題と一緒ですよね。提出してくれるチームもあるのですが、期限を過ぎても全然提出されないチームも複数あって、「早くアップしてください!」と全体メッセージで催促することもありました。Instagramの下の方にある「チームテック活動報告」や「チームRAV4 企画紹介」などが、各チームに作ってもらったPR投稿です。
―― 立ち上げから1年ほど経ちますが、SNSチームの現状はいかがですか?
Tさん 最初は3、4人で人数が少なかったので、「これで回しきれるのか?」という不安がありました。特に活動開始直後の4月から7月くらいはスタートダッシュが大事だということで投稿頻度を上げたかったのですが、人数が少ない中での運営管理は大変でした。
今はメンバー7人でやっています。僕が同級生に「SNS面白いから誰か入って」と声をかけたら、「僕、編集できるからやろうか」とか「今プロジェクトの手が空いてるからSNS行けるよ」という感じで2~3人が入ってくれて。編集ができる人は意外と少ないので助かります。つい最近1年生が1人参加してくれたし、少しずつ手伝いに来てくれる人が増えました。
―― 7人で役割分担はされているのですか?
Tさん はい、取材に行く人、撮影に行く人、編集する人、というように役割を分けています。例えば、アルプスの活動に取材に行く場合、1、2人がスマホで撮影し、現場の手伝いもしつつ、終わったらその人がなるべく編集まで担当するようにしています。
―― 撮影から編集まで一貫して担当するのですね。
Tさん 編集する人の意図によって撮影の仕方も変わるじゃないですか。僕の動画は文字を多く使うのですが、現場の雰囲気を文字で伝えるには、やはり現場にいないと難しい。だから、なるべく撮影から編集まで一人で完結させようと。もちろん、編集だけやりたい人や、編集はできないけど撮影ならできるという人もいるので、その場合は得意な分野で協力してもらっています。僕は撮影から編集までできるので、なるべく一人で完結させています。
―― 編集会議のようなものはありますか?
Tさん 編集会議はやっていません。編集はその人の個性が出るもので、「この動画、絶対あいつが作ったよね」と分かるようなものでいいと思っているので。それよりも、月1回、「来月のイベントに誰が撮影に行くか」を話し合っています。それよりも撮影をどうするか、という方が重要なので。
――逆に、この活動のどんなところにやりがいを感じていますか?
Tさん 編集作業は趣味なので楽しいですし、撮影で現場に行くのも楽しいですね。その現場でしか話せない人もいますしね。作った動画を「投稿できたぞ!」という達成感もあるし、再生回数が伸びているのを見るのもうれしいです。純粋にフォロワーさんが増えた時は「おっ」と、テンションが上がりますし、総合的に楽しいです。そういえば、村上先生から「企業さんにも注目されているよ」と言われましたね。
―― 今後のSNSチームとしての目標はありますか?
Tさん まずは投稿頻度を週2~3回程度に増やしたいです。以前、ラーニングバリューさんから他大学のInstagramの運用方法について教えてもらいました。その大学では曜日ごとに担当が決まっていて、ほぼ毎日何かしら投稿されているんです。それに比べてHIT-ALPsは投稿がない日が多いので…。
最近イベントが少ないので、月1回のミーティングで「この日は誰が投稿する」と決めても、素材がなくて遅れたり、結局ネタがなかったりすることがあります。それに、投稿ネタには賞味期限もありますが、編集が遅れも積み重なっています。個人的には、冬休みに動画編集を進めてストックを作りたいと思っています。
――チームのリーダーとして、それを実現するためのステップをどのように考えていますか?
Tさん まずはスタッフを増やしたい…いや、増やしすぎても管理が難しくなるので、今の7人でどれだけ効率よく投稿できるか、ですね。動ける人が効率よく動く、というのが目標かな。
あとは、投稿頻度を上げること。発信しないことには見てもらえないし、おすすめにも載らない。発信が止まっているからフォロワーも増えないのかな、と。発信するためにはスタッフの効率を上げないといけない…全部つながっていますね。
――SNSによるサポートを通して、HIT-ALPsがどうなっていけばいいと思いますか?
Tさん まずは、多くの人にHIT-ALPsを知ってもらうことが大事です。そもそもこの存在を知らない人も多いので。僕たちが作った投稿が、いろんな人のおすすめに載ることが第一歩。スルーされるかもしれませんが、まず見てもらわないとフォローには繋がりません。そのためには僕たちSNSチームが頑張って発信頻度を上げて、新しいフォロワーさんを獲得していく必要がある。そうして、HIT-ALPs自体の活動が評価されればいいなと思います。
―― ご苦労も多いと思いますが、頑張ってください。
※肩書・掲載内容は取材当時(2024年12月)のものです。
【広島工業大学編】他の連載ページへ

TさんはHIT-ALPsの卵ランプづくりプロジェクトに参加するともに、高校時代からの自主活動で培ったSNSへの発信の経験を活かして、HIT-ALPsの広報担当として、様々な情報をSNSで発信されていらっしゃいます。すなわちHIT-ALPsは、広報と言う部分にも学生の自主性を活用していくことを実現しているわけです。これは素晴らしいアイデアだと思いました。高校生にとっては自分たちとあまり年齢の変わらない先輩を通じた大学の情報や学生生活の情報には、きっと興味を持つだろうし、親近感も持つだろうと思うのです。
そして前回のインタビューでも感じましたが、先生方は授業態度や成績を通して学生さんの自主性を見ていることが多いと思います。それに加えて、もし個々の学生の興味や好きなことなどに関心を払い、それを伸ばす方向で自主性を育てることを意識してみると、学生さんたちはその何かに対して自主的に活動し始め、ひいては自主的に学びに向かう態度を育めるのではないか。そのためにも日頃から学生がアウトプットするような機会を作り、どんなことをアウトプットしてくるのか、その背後にあるのはどんな気持ちなのだろうか、そんなことを観察することが大切になるのではないかと感じました。