top of page
the Road of the school OD

学校の組織開発物語
記事を探す


連載3/人と関わる力量を保育者養成プログラムで養う【清泉女学院短期大学】
清泉女学院短期大学の幼児教育科では、特色あるカリキュラムのもとで保育者養成を行うため、2008年より『保育者養成のための初年次教育プログラム』をスタートさせています。入学前の『自分発見スタートセミナー』に始まるさまざまな学びの場を学生はどのように受け止め、成長しているのでし...
2019年12月16日
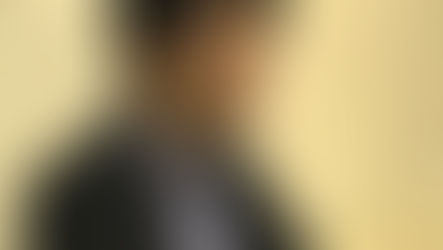

連載2-3/深い学びを引き出す教員のファシリテーションとチームワーク【清泉女学院短期大学】
入学前教育からスタートする「初年次教育プログラム」を皮切りに、2年間にたくさんの行事、活動に取り組んでいる清泉女学院短期大学の幼児教育科。「清泉ならではの保育者養成」を特徴づけるために始まったさまざまな試みは、実に多岐にわたっており、教員のみなさんの負担も決して少なくはあり...
2019年12月5日


連載2-2/深い学びを引き出す教員のファシリテーションとチームワーク【清泉女学院短期大学】
国家資格取得のために法律で定められたカリキュラムにとどまらず、初年次からスタートするさまざまな教育プログラムや実習、行事で学生の自主性を伸ばす教育に取り組む清泉女学院短期大学。濃密な2年間を過ごす学生のそばには、彼女たちの活動に伴走し、意欲を引き出そうとする教員の...
2019年11月25日


連載2-1/深い学びを引き出す教員のファシリテーションとチームワーク【清泉女学院短期大学】
キリスト教系の短期大学で、長年にわたる保育者養成の歴史と実績をもつ清泉女学院短期大学。特色のある保育者養成プログラムの構築に取り組む一環として、2008年より『保育者養成のための初年次教育プログラム』をスタートさせています。ただでさえ、国家資格取得のためのカリキュラムが目白...
2019年11月15日


連載1-4/学びを「補う&引き出す」ための初年次教育プログラム【清泉女学院短期大学】
2008年から『 保育者養成のための初年次教育プログラム 』をスタートさせ、特色ある教育を展開している清泉女学院短期大学の幼児教育科。学生にさまざまな体験の機会を提供すればするほど、教員の負担は増えてしまうのですが、実際現場で指導にあたる教員はどのように取り組んでいるのでし...
2019年11月5日


連載1-3/学びを「補う&引き出す」ための初年次教育プログラム【清泉女学院短期大学】
清泉女学院短期大学の幼児教育科で2008年からスタートした『 保育者養成のための初年次教育プログラム 』。これは保育者養成において学生に足りないものを「補う」(リメディアル)だけでなく、意欲を「引き出す」ことを重視したプログラムになっています。どのように意欲を刺激する仕掛け...
2019年10月25日


連載1-2/学びを「補う&引き出す」ための初年次教育プログラム【清泉女学院短期大学】
清泉女学院短期大学の幼児教育科では、特色あるカリキュラムのもとで保育者養成を行うため、2008年より『 保育者養成のための初年次教育プログラム 』をスタートさせています。カリキュラムの見直しが必要だと考えるようになった背景で、どんな現象が起きていたのでしょうか?短大が抱えて...
2019年10月15日


連載1-1/学びを「補う&引き出す」ための初年次教育プログラム【清泉女学院短期大学】
長野県長野市にある清泉女学院短期大学は幼児教育科、国際コミュニケーション科を擁するキリスト教系の短期大学です。保育者養成の歴史と実績を持つ同大ですが、卒業生の質にこだわるためカリキュラムの見直しに着手。入学前・初年次において、補う(リメディアル)&引き出す(学びの動機づけ)...
2019年10月7日


連載4-3/学生に気づきをもたらす学科の枠を越えた学びの場【神戸常盤大学】
医療と教育の専門職業人を育成する神戸常盤大学では、資格教育に偏重することなく、時代や社会の変化に対応できる人材を育成する教育を実践するため、初年次教育に《 まなぶる▶ときわびと 》(以下、まなぶる)を導入しています。学科の枠を取り払ったクラス編成でグループワークを体験した学...
2019年9月26日
Search by Univ
他の大学の記事を探す
bottom of page